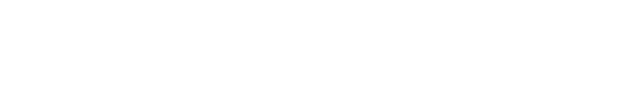副院長ブログ(「インシュリン物語」を読む⑮一 インシュリン以前 1 生き残った少年)
《インシュリン物語を読んでいます。ここで本の最初の章へ移ります。》
インシュリンの発見にまつわる物語ほど劇的な発見物語は少ない。
絶望と死からの跳躍は極めて急激であったし、しかも二人の無名の若者の文字通り没我的な努力で成し遂げられたものであるだけに、世人の心を惹きつけてやまないものがある。
インシュリンの発見後43年の1964年現在(当時)、インシュリンの奇蹟はますます意味を深めている。
今日世界中には1500万人以上の糖尿病患者がいるという。《現在は世界中で10人に1人、5億3700万人を越えています》
彼らの一人一人にとってまた家族達にとって驚異はやむことはなく、バンティングとベストに対する彼らの感謝は測りしれないものがある。
インシュリンの意義を明らかにするために、その背景を知り、1921年の発見以前の患者の治療がどのようであったかを考えてみるのは重要なことである。
1888年に医師の資格を得て以来ずっと糖尿病を扱い続けてきた糖尿病医の長老、故エリオット・P・ジョスリンほど完璧な答をしたものはいないであろう。
1960年、ジョスリン90歳の誕生日に親しく挨拶すべくカナダのトロントからアメリカのボストンに飛んだベストは「インシュリン以前の糖尿病治療はどんなふうでしたか」とジョスリンにたずねた。
(中略)
「インシュリンを手にした40年。インシュリンのなかった4000年。人類にとってそれはどのような意味を持っていたことだろう。
アメリカには300万人の糖尿病患者がいると考えられる。インシュリンはこれらの人々の平均寿命を少なくとも10年は伸ばしている」
1921年以来世界中で延命し生き残った人々の数を考えればインシュリンの発見と製造の意義は天文学的なものになる。
糖尿病の子供の運命は20世紀初頭でさえも紀元前1500年に既にパピルス・エベルスに記されている史上最初の症例とほとんど変わるところがなかった。
次の一症例はインシュリンが発見される前の糖尿病患者に起こったことを簡明に示している。
シカゴから遠くないアメリカ中西部の小さな町で、暑い8月の午後の静けさを破って玄関の網戸がばたんと閉まった。
アルバートはよろよろと台所の椅子に歩いて来た。
「お母さん、僕だよ。ボール遊びから先に帰ってきたんだ。だるくってしかたないんだよ。」
母親のウォーカー夫人は縫い物をやめ、背の高い痩せた14歳になる息子に何が起こったのかと急いで見に来た。
「まあ、だったら何か食べなくちゃあ、坊や」と彼女は言って、サンドウィッチを作るために食器棚のところに急いだ。
やがてアルバートは起き上がりサンドウィッチをおかわりし、大きなアップルパイを食べ、水を何杯も飲み、なみなみとついだミルクも飲んで再び横になった。
しかし食物では疲れは治らず、30分も経った頃、落ち着きのない苦しそうな眠りに陥ってしまった。
ウォーカー夫人は心配そうに息子を見守っていたが、やがて近いうちにライト先生に会いに行くべきだと心に決めた。
少年はちょうど成長期で、最近は他の子供より尿が近いことに母親は気がついていた。
ウォーカー氏もやはりアルバートの具合がよくないことを認めた。
翌日の午後早速、夫妻はアルバートを医師のところに連れて行った。
ライト先生は愉快な中年の医師であったが、この小さい町で医業で忙殺されていた。
彼は注意深く話しを聞いてから簡単に診察し、次いで尿を取ってくるように命じた。
尿を手にすると彼は診察室の後ろにある小さな試験室に入っていった。
先生は尿を入れた試験管を焔にかざして温めていた。
それから青い液を加え、それが沸騰すると、液は煉瓦色に変わった。
「さて、アルバート。君も大きくなったな。こういう成長期には特別な食事をし、十分に運動することが大変大切なんだよ。君は野球が好きかい?」
「ええ、先生、僕は今チームの捕手なのですが、ゲームを全部やり通せそうもないのです。終わるまでにすごく疲れてしまって家に帰らなくてはならなくなるのです。」とアルバートは答えた。
「アルバート、君の心臓を調べたのでは少しも悪いところはない。だから心配しないでいい。ただ、君が守らねばならない食事のことと、しなくてはならない運動のことはお母さんに話しておく。水をたくさん飲んで、十分に睡眠をとって、定期的にここに来なさい。ウォーカー夫人、明日のごごもう一度来て下さい。その時食事箋をあげますから。」
翌日の午後、医師は厳粛な、悲愴な面持で両親に向かって言った。
「残念ながら息子さんは糖尿病です。」
教師のウォーカー氏はこの言葉の意味をただちに理解した。
祖父が糖尿病だったウォーカー夫人もまた、医師の言葉の真意がよくわかった。
(中略)
食事箋として、甘味のつよくない果物、よく洗った糠で作ったせんべい、糖質のごく少ない肉や野菜のリストと、清涼飲料水・砂糖・オートミール・パン・あらゆる種類の澱粉・甘いプディング・飴・菓子・ジャム・ジェリー・甘い漬け物などおよそ成長期の少年の好みそうなものを全部禁じた厳しい制限リストを手渡した。
困難な治療法ではあるが、それが唯一の治療法であった。
「十分に運動させて、たくさん水分をとらせてください。」とライト医師は続けた。
「もし変わったことがあったら、すぐに私のところによこして下さい。たとえ何も変化がなくても毎月私のところに来させて下さい。」
成長期に糖尿病を発症した少年は週毎に身体は少しずつ痩せてきて病気が重くなるにつれてたくさんの食物を必要とするように見えたが身体が利用できる食物は少なくなって、遂にはどんなに厳重に食事を調節しても血中に糖がたまるのが防げず、有害な物質も血中にたまって、最後には意識を失って、時には肺炎に、、、
しかしアルバートの場合は違っていた。
彼は1920年8月に糖尿病を発症し、1921年の秋までには致命的な昏睡には陥っていなかった。
その頃、あるシカゴの専門家がトロントで発見された新しい治療薬のことを耳にして、ライト先生のためにこの救命薬、インシュリンを少し手に入れてくれた。
糖尿病の少年アルバートは有名な医師になって、今日(当時)なお開業医として活躍している。
バンティングがハイスクールの少年だった頃、同級生の少女がだんだん痩せ衰えて数ヶ月のうちに死んでいくのを見た。
当時、助言できることといえば飢餓食を食べさせることであったが、それでも、若い患者の場合には数ヶ月、チャールズ・ベストの伯母のような高年者でもおそらくは数年だけ命を延ばすだけであることは誰もが知っていた。
アンナ・ベストは1915年2月にボストンのジョスリン先生に会いに行った。
当時30余歳の看護師アンナの病歴は体重の漸減と尿糖の出現という典型的なものであった。
数年間、糖質の乏しい食餌療法をして生き延びていたがジョスリンの言葉を借りれば「彼女は生存はしていたが糖尿病昏睡で死んだ1917年の5月までは体重は減る一方であった。」
(中略)
イギリスのある若い医師が手術中に骨片が顔に飛んで眼を怪我して敗血症となったが尿検査により糖尿病を診断された。
彼はイタリーに移り、静かな開業生活の中に控えめな生活で高蛋白食と糖質の低い辛口白葡萄酒を飲むことができた。
この食餌療法は糖尿病者の生命を少し延ばすように見えたが、失明、感染、壊疽の重篤な余病の併発が進んでいた。
ある日のことロンドンにいる親友の医師から「スグカエレ、インシュリンガデキタ、コウカアリ」と電報が届いた。
彼はこうして生へと呼び戻され、後に糖尿病学における指導的専門学者になった。このひとR・ローレンス卿は今日(当時)もなお活発な活動をして同病の糖尿病者を助けている。
参考書:インシュリン物語 G.レンシャル・G.ヘテニー・W.フィーズビー著 二宮陸雄訳 岩波書店 1965年発行 1978年第12刷版